※『ヴァージン・ウルフ』の3ヵ月前
ショッピングモールの吹き抜けには七夕を彩るみごとな笹が何本もアーチのように飾ってあった。薄い折り紙を割いた原色の短冊たちが弱い空調に吹かれている。モール内の文房具屋さんに寄った帰り道、竹藪のなかに迷いこんだような気持ちでゆっくり笹のアーチをくぐり抜けると、ちょうど、エントランスを入ってすぐのエスカレーターが目の前に伸びていた。背後でからからと乾いた笹の葉と紙切れが鳴る。
わたしたちはそのとき、確かに見つめあった。宮くんの切れ長の瞳がわたしの視線のなかで立ち止まった感覚があった。あ、と、唇が震える。そしてすぐ、不用意な反応を洩らしたことに後悔をした。背の高い彼の影に隠れて、そのとなりに、見知らぬ女の子が歩いていたから。彼女が先にエスカレーターに脚をかけ、ふたつ上の段差から宮くんを振り返る。宮くんはぞっとするほど自然なタイミングでわたしから目を逸らし、彼女に向けて何か相槌を打って笑った。
店内を流れる静かなBGMも、涼しげな笹の葉鳴りも消えて、心臓の軋めく音だけが鼓膜を揺らす。わたしは、そんなわたしに驚いていた。少なくとも、彼がわたしじゃない女の子を連れだって歩いていることよりもずっと、それはわたしを呑みこむ一大事だったのだ。
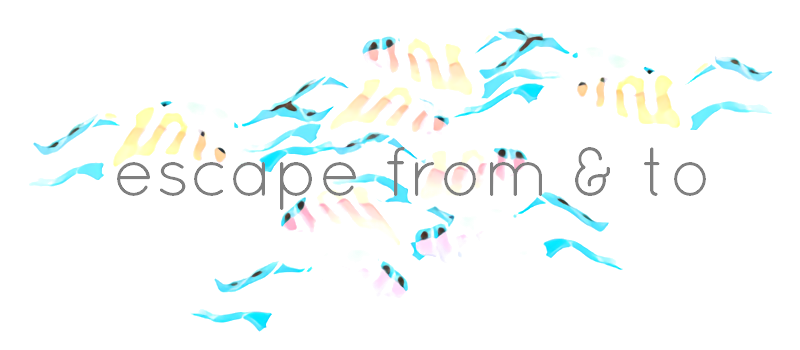
四限の理科室での授業から一旦教室に戻らずに図書室へと足を向けると、そこには思わぬ先客が居た。図書委員を務めていた去年までの癖みたいなもので、今でもよく図書室にお世話になっているし、背の高い本棚に囲まれているとふしぎと色んなことが捗るような気がした。勉強も、考えごとも。向かいの通路で本を手にとるでもなく仁王立ちしている彼は、とても、探しものが捗っているふうには見えなかったけれど。
「宮くん、課題の探しもの?」
彼は振り向き、通路の端から顔を覗かせていたわたしを見とめるとわずかに目を見張った。ちょっとのことではひらめかない冷めた顔立ち。瓜二つの容れものを持っていたとしても、なかには全く違う生きものを飼っているのだと、こんなささいな表情にも思わされる。
「……あの俺、」
「うん。おさむくん、やろ」
「あ、はぁ」
「いつも眠たそうやからわかる」
「不名誉な区別やな……」
ごめん、と言って笑うと、宮くんもこめかみのあたりを指のはらで掻きながらめずらしく気抜けた笑みをみせた。ズボンのポケットのなかから隠していた大きな右手が出てくる。それは年上の知り合いに対するわずかな礼節というよりも、警戒心をひとつほどくようなくつろいだそぶりだった。
「もしかしてしげちゃんの授業のレポート? わたしもこのへんで本探したなあ」
彼のとなりに寄って目の前の本棚を上から下まで眺めると、彼が何を悩んでそこに立ち尽くしていたのかなんとなく察しがついた。二年生の地理を担当している先生は厳しくて、受験に特化した授業を嫌い、夏休み前になると必ずちょっと大きめのレポートの課題を出すのだ。まだかろうじて残っているとっつきやすそうな本を数冊、背表紙に指を引っかけて手に取る。その資料を受け取りながら、宮くんはずっとわたしの指の動きを目で追っていた。何かを、つぶさに観察するようなまなざしで。
「先輩って、」
「うん?」
「いや……先輩ってまだ侑から逃げとるんですか」
腕のなかの本を物色しながら、宮くんはぼそっとその名前を口にした。途端に頬に血が集まる。自分ではどうにもならない、不自由な熱。
「逃げ、っ、なにそれ」
「よーゆうてるから、あいつ。なんでいっつも逃げんねやろって」
どんなとき、どんなふうに、どんな気持ちをこめて彼はそんな口ぶりで話すのだろう。双子の兄弟の距離は分からないけれど、彼の目に映っている自分の姿が、きっとこの頬に溜まる熱のように情けないのだということは分かる。逃げている、なんて。表向きどんなに穏やかに接していても、その裏で彼の目にはわたしがそういうふうに映っているのだろう。
「……逃げてるのかな、わたし」
「いや、知りませんけど」
当たり前の答えが返ってきて、ごまかすみたいに笑って、頷いた。本の匂いの染みこんだ静けさが耳に痛い。いつもならこの、誰もが気兼ねなくひとりでいられる空気が好きなのに、今は内側にこもっている熱の騒がしさを咎められているような気がしてならなかった。
入学式での奇妙な出会いから、宮くんとはずっと、あたりさわりのない距離で話したり、笑ったり、試合の応援に誘われ、体育館へ足を運んだり、昼休みを一緒に過ごしたり、たぶん小学生でもできそうなことばかりを繰り返している。高校生の男女らしいことと言えば、一度だけ、二人で遊びに行った。去年の夏に、ちょっと有名な花火大会へ。はぐれるから、という凡百な理由で手をつないだとき、わたしたちは代わりに遠ざかる理由を手放してしまったような気がする。付かず離れず、と言い表せば多少は見栄えがするのかもしれないけれど、二人ですすんでこの距離を選びとっているのかと問われれば、きっとお互い押し黙ってしまうだろう。
「先輩が逃げとるいうより、あいつが追っかけすぎてんのかもしれませんね」
宮くんはふしぎなことを言う。誰も逃げないものを追いかけることはできない。それに、わたしの目に映る彼は「追っかけすぎてる」という指摘に似あうような熱心さを持て余してはいなかった。律儀だな、という温度で、彼はわたしに接する。そこに熱はあるのか。わたしの頬を支配しているのと、同じような。
「ありがとうございます。この本、いいですね。これにします」
ぱちん、と本の表紙を閉じる音がして、呼び覚まされたときにはもう、宮くんはさっさと歩きだしていた。空いた棚に設置されている返却ボックスに不要な数冊を押しこんで、選びとったらしい一冊だけを脇に抱えている。思わず、釣られるように足を一歩踏みだしていた。軽い会釈をして彼が振り返ったとき、ずっと喉に引っかかっていた言葉が舌に触れた。止まらなかった。
「あっ、あの、宮くん」
「はい」
「あ……えっと、きのうの放課後、駅前のモールおった? 五時ぐらいやったかな……」
言葉にすると、言葉ではないものが、舌を突きさす苦みのように蘇ってくる。昨日の夜、何度も何度もからだから追いだそうとしたあの一瞬のこと。考えたくないのに考えてばかりいること。手にしていたノートとペンケースを胸にきつくきつく抱きしめる。縋っているのは、藁よりももっと頼りないものだと分かっているのに、それでも自分の手で、足で、泳ごうとしない。溺れるのは、誰だってこわいものだから。
「わかるんちゃいます。先輩なら、それが俺か、俺やないのか」
思いがけずきっぱりとした目つきで、宮くんはわたしを見据えた。しつれいします、と足音が遠のき、薄暗い本棚のすきまにひとり、何かを諭されたような気持ちで取り残される。誰に尋ねるまでもなく、こたえはもう変えられなかった。二人の見た目が似てるとか、うっかり見間違うとか、そういう問題じゃない。わたしは彼に傷ついた。目に見えるものがどうだったとしても、目に見えない不安のかたちはもうけっして変えられない。
・
・
・
いつも一緒に帰っている友人が職員室に寄る用事があるというので、放課後、下駄箱に向かう前に生徒休憩室に立ち寄った。壁伝いに並んでいる自動販売機と、ちらほらと埋まっている丸テーブルをすり抜けて、中庭に面した窓際のカウンター席に腰を下ろす。今週から期末テストの準備期間に入ったせいか、休憩室はいつもの放課後より心なし混みあっていた。
昼休みのことを考えていた。膝に乗せた参考書にも目を通せないまま、ぼうっと窓の外を見つめていた。だから、真上の蛍光灯の明かりが遮られたことにも気づかなかった。やわらかく肩を叩かれるまで、ずっと。
「せーんぱい、ひとりで何してるん」
耳になじむなめらかな声が降る。手のひらは慎ましくすぐに剥がれても、彼に触れられたそこには何かが残り続ける。振り返ったわたしの顔を上から覗きこむようにして、宮くんは「めっちゃ驚いとる」と言いながらきらめく湖面のように笑った。すくむほどに爽やかな宮くんのすがた。一日過ごしても白いカッターシャツは清潔に整っていて、ベルトを締め、ズボンに仕舞いこんでいる裾も腕まくりした袖もだらしなくない。彼はちょっと、身なりには潔癖なところがある。いつも通り、きのう通り、何も変わったことなんてない。だからこそ、自分のなかの変化が分かる。わたしが今日けっして出くわしたくなかったのは、彼ではなくて、彼と二人でいるわたし自身だった。
「渡り廊下から先輩のこと見つけてもうて。先輩まだ帰らんの?」
「……あ、う、うん。友だちのこと待ってる」
「じゃあお友だち来るまで俺とお話ししましょー」
宮くんはよく、「俺とお話ししましょ」とか「俺と購買行きましょ」とか「俺のこと観に来てください」とか、言う。いつもささやかにわたしを縛る、わたしを囲う、彼の口癖のようなもの。胸のなかに巣食っていた張本人がいきなり飛びだして現れたようで、どうにも落ち着けないまま、それでも小さく頷くと、宮くんは通学かばんをテーブルの上に乗せてわたしのとなりのイスを引いた。ちょっとだけイスの向きを斜めにして、膝が触れ合いそうな距離に彼が座っている。いよいよ肩が縮こまった。いつものように話さなきゃ、そう思うほど、喉が閉じて呼吸すらもつたない。
「そうや先輩のクラス、体育祭の種目ってもう決めました? まだ? うち明日のHRで決めるんやけど。先輩が出るやつ、俺も出よかなあ。せやったら休み明けの昼練もサボらずに楽しめそうやし……」
中庭の木々が揺れ、宮くんの紺色のかばんの表面や、わたしの膝上のよれたプリーツ、二人の四本の腕に、ひかりの粒子がざわりと散らばる。彼とあまり目を合わせないようにして、彼の差しだしてくれる話題に適当な相槌を打っていたはずなのだけど、その場過ごしの「ふつう」の擬態はそう長くは続かなかった。息継ぎのあいだで、宮くんが初めてお喋りな唇を閉じる。髪を掻いて、そして軽く組んでいた足先をほどいた。
「あかん、今日の先輩無口や」
「……えっ?」
「昨日ごめんなさい。声かけれんくて、無視したみたいになった。怒ってます?」
宮くんのなかではきっとあんなの大したことではないのだと、そう思い始めていた矢先に、彼ははっきりと正面から昨日のことを口にした。ごめんなさい、と。過剰なぐらいこちらを窺うような瞳をよこして。そんな目をされたら、今度こそあんなすれ違い大したことないのだと、飲みこまないといけないような気がしてくる。頭では頷いても、自分の言葉で返事をしている実感がなかった。
「怒ってないよ、そんな……宮くん、ひとりやなかったし。わたしも、挨拶も何もできひんかったから、お互いさま」
耳を傾ける宮くんの表情は真剣で、わたしの返答はばかみたいにお粗末だった。会話が途切れる。いやな間がひろがる。宮くんはたっぷりと沈黙を味方につけてから静かに口をひらいた。
「あれね、バスケ部のマネの子です。備品の買い出しの手伝いやらされてたんです。ひと使い荒くてあいつ。俺バレー部やのに……」
宮くんは膝の上で長い指と指を絡ませたりほどいたりしながら、昨日のことを話した。目の遣り方にも、その指の動きにも、端々に芝居がかったためらいが滲んでいる。そんなふうに思う。だけどそれは、かえって彼にしてはめずらしい年下然とした仕草でもあった。宮くんと話していると、自分のほうが年上だということを忘れそうになる。「先輩」としか、呼ばれたことないのに。
「そう、なんや。大変やったね」
「ほんまですよ、あのあとめっちゃ荷物持たされて。……まあ、せやけど、普段世話になってますからね。こっち女子マネおらんし、ほら、書類の整理とかこまいことは女の子のほうがよう気ぃつくんですよ」
「うん、わかるよ」
彼が何をそんなに、饒舌にわたしに説明してくれているのか分からなかった。そんなことが聞きたいわけじゃないと拒んでいたからかもしれない。わたしの知らない、宮くんの世界。その世界に、女の子がいる。傷ついてはいけない当たり前のことだ。はやく、はやく、と念じているのに友人からの連絡はまだこない。だから、小さな嘘をついた。かばんのポケットからスマートフォンを取りだして、握りしめる。なんの通知も出ていないまっさらなロック画面を一瞬だけ光らせた。彼に気づかれないように。
「ごめん、友だちからメール来たから、行くね」
つらつらと続く彼の話をなかば遮って立ち上がる。口を噤んだ宮くんは、そのぶん大きな目でわたしを見上げた。膝の上の、指先のたわむれをぴたりと止めて、彼は幽かな笑みを貼りつける。
「……そか。んじゃ、先輩また」
「うん」
一行も読めなかった参考書をかばんに放りこんで、わたしはようやく宮くんの視線を視線で受けつけた。うかつだった。そうしよう、と思ったわけじゃない。偶然か、あるいは彼がそうしようと思ったのだ。はやく、はやく。おざなりな手つきでイスをテーブルに寄せようとしたとき、背もたれに掛けた手を、鋭くつかまれた。彼の手は熱かった。いつだって軽やかな彼には似つかわしくない、重たい熱を放っていた。
「やっぱあかん。ちょお待って。一分」
ひとつまみも笑うところのない眼力でぎりぎりと見つめられる。手首に感じる握力もそれに比例して膨らむ。は、と口もとを緩めても、それはもう優しさの記号ではない。彼が抑えこもうとしている怒りが腕から伝ってきて、自分のずるさを胸に突きつけられているような気がした。
「なんかめっちゃ気まずう、これ。なんや。先輩、なに? なんか言うてよ」
なんっにも話せた気がせえへん、と彼はさらに語気を強めた。こんなに感情的になっている宮くんと向かい合うのはもちろん初めてのことだった。この一年と数ヵ月、ほんとうは喜怒哀楽すらまともに分かち合えていなかった。宮くんと良い友だちになれるとか、思ってない、全然。わたしたちはどうして、なんのため、コンパスで描いたようなお行儀のいい距離を保っているの? それを考えるといつも全身がすくんだ。
「なにって、なに……そんなの、」
腕をゆする。びくともしないで、鈍い圧迫感に負け、美しくて退屈な円がみしみしと音を立てて壊れていく。
「離して、宮くん」
「いやや、逃げる。いま逃げられたら、わからんくなる」
「なに……逃げてへん」
「逃げてるよ、いつも」
腕を引っ張られたせいか、毅然とした声に圧しつけられたせいか、足の踏ん張りがきかなくなってわたしはイスに崩れ落ちた。抵抗をやめて膝に腕を置く。ようやく離れていった宮くんの右手が、彼自身の左胸に辿りつくのを、目で追う。かつてわたしが白い花を縫いつけた、少しずるがしこい彼の心臓。くしゃりとシャツをつかみ、宮くんはわたしから視線をはずさず、身を乗りだすようにして言った。
「なあ、先輩のここにあったモン、今どこにあるん? どこ逃げてんの? 全然動いてへんってことはないやろ。俺やって、こんな……」
彼が言葉を詰まらせまつげを何度か揺らす。高い天井に反響するざわめきのなかで、細い声がうまく聞き取れない。なんにも話した気がせえへん、という彼の訴えはきっと、今までのわたしたちそのものだった。無難に笑いあうことで、ぎこちなく取り繕うことで、思いこみと思い過ごしで、ここまで流されて来た。命のめぐりではないものが胸の内側を蹴るたびに、未知の方角へとわたしは傾き、そんな自分をずっと放ったらかしにしていたのだ。
「……動いてる。動いてる、よ」
睨むような目つきが、一転してさみしげな痛々しい表情になり、かわるがわる訪れる宮くんの動揺を前に、自然とわたしも声を張っていた。自分に言い聞かせるような、どうしようもない声だったけれど。
「勝手に動き回って、どっか行って……宮くんのせいで迷子や、もうずっと」
耐えきれず俯いてしまった頭に、そっと、何かがさわる。同じように俯いた宮くんの頭が押しつけられている。落とした視線の先で、彼の手がわたしの手を包みこむ。こんな休憩室の端っこで、誰に見られているとも分からないのに、宮くんの撫でるような、正攻法からそむくような温もりは止まなかった。
「先輩。それ、そろそろ見つけてあげよ」
悲しいことも悔しいことも何もないのに目頭にぶあつい負荷がかかって、このままではいけないと視線をもたげると、彼もまるでわたしを映す忠実な鏡のような瞳をしていた。わたしは今まで一度も、彼に自分と似たものを感じたことはない。きっとこれからも、滅多にそんな都合のいい幸運は見つけられないと思う。見つからないほうがいい。こんな目をずっと見ていたら、わたし、どうにかなる。
「見つけるって……」
「好きや。大好きや。もう俺から逃げんで」
まるでずっと前からその場所に、そのための隙間が用意されていたみたいに、自分の一部だったように、彼のくれた告白が深い淵へと沈んでいく。言葉、だけじゃない。彼の頭がぎゅうっと重みを持つ。そんなふうにしたらいつも寸分の狂いもなく整っている前髪が、きっと崩れてしまうだろうに。わがままな切実さを押しつけられているみたいで、余裕のないひたいの熱すら、とてもいとおしかった。
「……わたしも宮くんのこと、好き」
ひたいとひたいを合わせたまま、わたしたちは息をひそめて見つめあった。ふと近づいてきた唇に、びっくりして顔を上げようとすると、つないだままの手を引っ張られ、ごつんと間抜けな痛みを帯びてまた二人のひたいがさやかに馴染みあった。
彼の薄い唇があらためて角度を変える。こころよい鳥肌がたつ。宮くんはいつものいたずらっぽい笑みを含んだその唇で、「やっとつかまえた」とわたしの耳を夕陽のように染めあげた。
THE END
2017.7