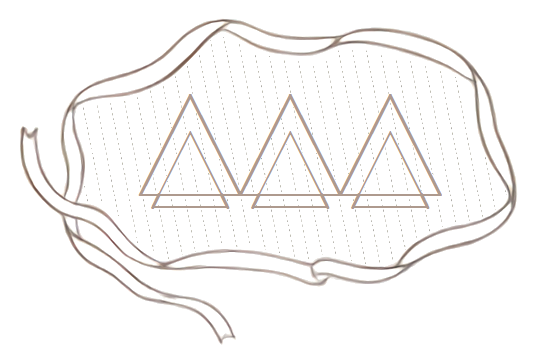
Ⅰ 夏の背中 - 1
年に一度のはなやいだ宵闇の景色に浮足立っていたら、神社の階段をひとつ大きく踏み外してしまった。慣れない身なりをしているせいで、とっさの動きもぎこちなくて頼りない。引力に逆らえずしりもちをついた瞬間、手首に下げていた赤と水色のヨーヨーが石段の角にぶつかって脆くもぱちんと弾けて割れた。ささやかな水しぶきがあがって、浴衣の裾と、石段の色をじわりと変えてゆく。砂利に浸みこむ水のゆくえが、ちょうちんの薄明かりの下でぼんやりと光の河のように浮かびあがっていた。
七月の終わりの夜は今日も蒸し暑くて、ほんとうだったらノースリーブにショートパンツを合わせたような身軽な服装が好ましいところだ。そんなことは百も承知で、女の子たちは不慣れな衣装に袖を通し、足の痛みをこらえて下駄を履く。おしゃれは我慢。そんな殊勝な根性ははなからないけれど、ようやくなんの変哲もない白のブラウスと紺色のスカートから開放されて、夏本番がやってきたのだ。少しくらいのへまはしたって、今ぐらいは日常を脱ぎ捨てていたい。高校生活最後の夏休みとなれば、なおさらに。
「あーあ、派手にやったな」
呑気にそんなことを言いながら、後ろから足音が近づいてくる。割れてしまったヨーヨーの残骸を拾いあげながら、鉄朗は私の座りこんでいる段差のひとつ下の段にゆっくりと膝をついた。ふつう、彼氏というものはこういうときもう少し慌てて助けにきてくれるものではないでしょうか。彼女が転んでしまったのなら、いたわる言葉をひとつ、ふたつ。なんて、柄にもないことを今さら確認しあうような二人でもないけれど。黒髪の奥にちらついている切れ長の瞳がまなざしていたのは、私の左足からこぼれた下駄の片割れだった。ちりめん模様の鼻緒がぷつりと切れて、とても履けないしろものになってしまっている。行き場のない素足を手のひらでさすってみると、指先にはいつの間にか小さなたこができていた。
「いっ、」
「捻ったか?」
「ううん……ちょっと擦りむいただけ」
「なるほど、んじゃ裸足で歩いて帰れるな」
良かった、良かった。わざとらしく朗らかに笑って、鉄朗が私の頭をわしわしと撫でる。まるで飼い猫をかわいがるみたいに。それは彼のお決まりのからかいの仕草だったので、おろしたての下駄もせっかく釣り上げたヨーヨーも一気に潰してしまったひとの気もしらないで、という恨めしい気持ちになってついつい彼のことを睨んでしまった。雑木林を抜けてきた境内の喧騒がやわらかに耳に届く。まだ、夏のさかりの余興は続いている。私たちのように石段を降りていくひとよりも、のぼっていくひとのほうがずっと多い。お祭りに集い、すり抜けていくひとたちの高揚に照った表情を見るのは好きだけれど、こんなところにしゃがみこんでいては何ごとかと逆にじろじろ見定められて、それだけのことで私の心は情けなさと恥ずかしさにすっかり萎んでいってしまった。
頭を撫でていた鉄朗の大きな手が、これでおしまい、とでも言うようにぽんぽんと軽やかに前髪に隠れた額のあたりを叩いた。いつものよれたTシャツに、いつものブルージーンズ。お小遣いを貯めて買ったというホワイトフラッグスのハイカットスニーカー。無造作な髪も、さまになる。男の子は、身軽でいいな。鉄朗はいじけた色を宿した私の瞳をいなすように、優しく眉を下げた表情をした。分かりきった種明かしの顔。最初からこうして笑ってくれたらいいのに。
「冗談だって。ほら、ちっと辛抱しろよ」
「わっ」
鉄朗の器用な指先がするりと私の右足からも下駄を奪ったかと思うと、彼はしゃがんだままその大きな背中を私に差しだしてきた。下駄を掴んでいるのとは逆の手のひらを上に向け、はやく乗れと言わんばかりの手招きまでして。
「特急、家ゆき。間もなく発車です」
「……嘘だ、快速くらいでしょ」
「それはお前の体重しだい……ってェ!」
渾身の力で背中を平手打ちしてから、文字通り遠慮なく、彼の首にしがみついた。そうするしかなかった。鉄朗の背格好は高校生の男の子としては平均よりずっと大きくてがっしりとしているから、私なんかがちょっと背中に乗ったくらいではまったくびくともしない。近所の神社から、いつも通り歩けば十分程度の道のり。浴衣は窮屈だし、向けられる視線はやっぱり気になるけれど、それでも裸足でコンクリートを踏みしめていくよりはずっと恵まれた帰り道になる。しんなりと汗で濡れた背中の感触も、その匂いも、熱も、彼は「辛抱しろ」と言ったけど、けっしてこの心臓の音を誤魔化してはくれないだろうと思った。私たちきっと、お互いに思っている以上にちゃんと「恋人」をしているから。どんなにふざけあっていても、温もりが触れればこの身に余るひとつまみの緊張が、いつだって二人の自由を少しずつ奪っていってしまうのだ。
それにしても、こんなふうに誰かにおぶってもらうのなんて、一体何年ぶりのことだろう。最後にこうしてくれたのはきっとお父さんか、親戚のお兄ちゃんか。ひとり、ふたり。こうやって私のことを軽々と抱えられるひとは、十何年分の思い出のなかにもそう何人もいるわけじゃなかった。
「なんだか不吉だよね」
「不吉じゃなくて、不注意の間違いだろ」
「そうだけど」
「大丈夫だっつの。迷信に喰われるような男かよ、お前の幼なじみは」
――そして、もうひとり。私にずっと背中を向けていたひとがいる。そっぽを向かれていたわけじゃなくて、ただ前だけを向いて、いつも私の斜め前を歩いていた男の子が。
私にはコウちゃん、もとい、木兎光太郎、というめずらしい名前の幼なじみがいる。幼なじみは、幼なじみ。同じ住宅地で、向かいの家に生まれ育った、同い年の男の子。ひとりだけ勝手にすくすく大きくなって、いつの間にか彼は、たったひとつの才能を生かしてどこにでもがむしゃらに突き進んでゆけるひとになっていた。今はここから電車を乗り継いで一時間半以上かかるバレーボールの名門校に通っている。同じ都内なのだから実家から通えなくもないけれど、朝晩の練習時間が短くなるのを嫌って、一年生の夏休みが明けてから彼は高校の寮に入っていた。だから、幼なじみと言っても顔を合わせる機会は今となってはそんなに多くない。ひとつのことに没頭して、彼の眼は今、きっとあの三色のボールの軌道しか見えていないのだろう。
「明日の午後、あっち行くんだったよな」
鉄朗の低い声が宵闇にすっと溶けていく。神社を離れて、車の通りも少ないのどかな舗道をしばらく行くと、いつの間にかあたりは夜の静けさにとっぷり浸かっていた。ついさっきまで賑やかさの只中にいたものだから、余計にそう感じるのかもしれない。
「うん。初日の第一試合だから前乗りするんだって。お父さんたち、張りきっちゃって」
へー、と気のない相槌を打って、鉄朗は一度、腕にかかる重みを払うように私の足をおぶいなおした。
コウちゃんの通う梟谷学園にとっては三年連続の出場になる夏のインターハイが、いよいよあさってから始まる。五日間の日程で夏の日本一が決まるのだ。一年生のときからコウちゃんはずっと試合に出続けていたけれど、毎年地方で行われるインターハイの本戦を私はまだ一度も観に行ったことがなかった。だから、コウちゃんにとっては三回目でも、私にとってはこれが最初で最後の一度きりのインターハイということになる。小さなころから仲の良い親どうしの旅行計画に巻きこまれるようにして、私はこの夏初めて、幼なじみの雄姿をこの目に焼きつけに行くのだ。
「早く帰ってこいよ」
「それ、コウちゃんにさっさと負けろってこと?」
「いやいや、練習終わりのアイスが」
「たまには自分で買ってきなさい」
額を彼の後頭部にぎゅう、と押しつける。かすかな汗の匂いの奥に、嗅ぎ慣れた清潔なシャンプーの香りが隠れていた。バレーボール漬けの毎日を送っているのは何も、幼なじみだけじゃない。今年の夏もずっと、私の恋人は学校の体育館で来る日も来る日もボールを追って過ごすのだろう。差し入れのアイスを一緒に食べる十分間だけが、二人にとってささやかなデートの時間になる。夏に限らずだいたいいつもこんなものだし、いいかげん慣れっこではあるのだけど、やっぱり周りの子たちがはしゃぎ尽くすこの一ヶ月半だけはいつもと違ったさみしさを覚えてしまうものだった。
「どした、急に黙って」
眠いんか。あやすように言葉をかけられ、ぼうっとしていた意識が呼びだされる。ゆりかごのような心地良い揺れ。歩くよりもゆるやかな速度。熱。眠気を誘うものばかりが二人にまとわりついていたけれど、彼に重みを預けながら居眠りができるほど私はまだ彼の前で無防備にはなれなかった。別に、猫を被っているわけではないのだけれど。
「ううん。ただ、もう二年経つんだなって」
二年。長いようで、短いようで、やっぱり長い月日が流れた。彼と出会って、三度目の夏。私にたくさんの初めてを教えてくれたひと。たくさんの初めてを一緒に迎えてくれたひと。二年という時はひとりの男の子をかけがえのない大切なひとに変えてしまうには充分すぎるくらいの時間だった。少なくとも、私には。二年前の二人のぎこちなさを思えば、私たちはそれなりに滑らかに二人きりをできるようになったと思う。
目の前で信号が赤に変わって、鉄朗は小さな横断歩道の前で歩を止めた。目の前をスクーターが一台、エンジン音を響かせて通り過ぎてゆく。この信号を渡りきれば、私の家はもうすぐそこだった。
「……まだ二年だろ、たった」
私に応答を求めているような、そうでないような、なんとも言えない微妙な声音だった。もう、でも、まだ、でも、どちらでも構わないような気がする。同じ時の流れはどこにもなくとも、信号待ちのささやかな一瞬をつかって私たちはきっと同じ日のことを思い出しているのだから。高校一年生の夏休み、二年前の七月の終わり。私たちは今日と同じようにあの神社の石段のふもとで落ちあったのだ。
・
・
・
私と鉄朗を引きあわせたのはコウちゃんだった。もっとちゃんと言えば、彼の存在ではなく彼の不在が私たちを出会わせてくれたのだと思う。
同じ音駒高校に通っているとはいっても、同じクラスでもなかった一年生どうしに特別な接点などあるわけでもない。別々の高校に通っていても、同じスポーツをしている者どうしのほうが、分かちあえるものは格段に多かっただろう。音駒と梟谷はしょっちゅう練習試合をしていて、音駒の体育館を使うときには私もたびたび試合を見に行っていた。そのときコウちゃんとは二言三言、先輩たちの目を盗んではなしをする機会はあったけれど、ほんのそれきりだ。だから、コウちゃんから「黒尾が今度、三人で遊ぼうだってよ」と話を持ちかけられたときには何がなんだかさっぱり分からなかった。あげく、二人を取り持つはずのコウちゃんが「インハイ直前の特練入った」などと言って約束をドタキャンしてきたものだから、私はなんの心の準備もできないまま、名前と顔をかろうじて分かる程度の男の子と二人で宵闇に放りだされてしまったのだ。
「あー……、今日はやめとく?」
バツの悪そうな顔をして、指で頬をかく。その、本当に申し訳なさそうな物言いに、身構えていた心が少しだけ楽になったのを覚えている。せっかくのお祭りの夜を前にして「やめとく」なんてもったいない。小学生のころから毎年ずっと足を運んでいる、近所の神社のお祭り。ときにはクラスの友達と、ときには家族と、そして幼なじみと。色んな記憶が今もスライドショーのようによぎるけれど、あの夏をさかいにここはたったひとりの男の子との大切な思い出の場所になった。
「どうして?」
「いや、だって、いきなり見知らぬ男と夜に二人っつーのも……」
自分から誘ってきたはずなのに「見知らぬ男」なんてへんてこな言い回しを真剣な顔をしてするので、ついつい空気も読まずに吹きだしてしまいそうになった。ほとんど初対面ではあるけれど、見知らぬ者どうしというのも少し違うだろうに。その言葉ひとつ、表情ひとつが、私の心を丁寧にすくって外さない。彼は出会ったときからずっとそういうひとだった。だって、気に入らない理由なんてひとつも持ち合わせていないのだもの。ずるい。彼はとってもずるい。それは、今でもときどき密かに思っている。
「私は気にしないよ。黒尾くんさえ、見知らぬ女と二人でよければ」
黒髪の奥で、赤ちょうちんの光を吸いこんだ瞳がひらめく。はっとするのは、例えばこんなとき。きつそうな顔立ちにこうして温もりがともったとき。
「……じゃあ、ま、見知らぬ者どうし楽しみますか」
こうして私たちは「見知らぬ者どうし」から少しずつ「見知った仲」になっていった。お互いの気持ちをゆっくりとなぞり、ようやく付き合いはじめたのは夏が終わって、少し肌寒くなってきたころのことだ。
・
・
・
「冬はもっと、鉄朗の応援もしたいな」
夏のさかりに冬の話をしても、今の私にはまだあまり現実感のないことだった。のんびりしているうちに今年もあっという間に季節は変わってしまうのだと、頭の片隅では分かっているのだけれど。信号がぱっと青に変わって、まるで私の言葉を合図にしたかのように鉄朗が再び歩きだす。日が落ちると心は少しだけお喋りになる。どうしてだろう、闇に隠れてしまえるものは目に見えるものだけのはずなのに。
「任せなさい」
夜風がほつれた後れ毛をさらって、内側に渦巻いていた熱のかたまりが一緒になって心地良くほぐれていく。それはちょっとおどけているようで、何よりきっぱりとしたあなたらしい一言だった。その誓いのゆくえを見届けてみたい。できれば、あなたの息遣いや、温度を知ることのできる今のままの距離で。七夕はとっくに過ぎてしまったけれど、東京の星のない夜空にそんな願いごとをひとつ放った。