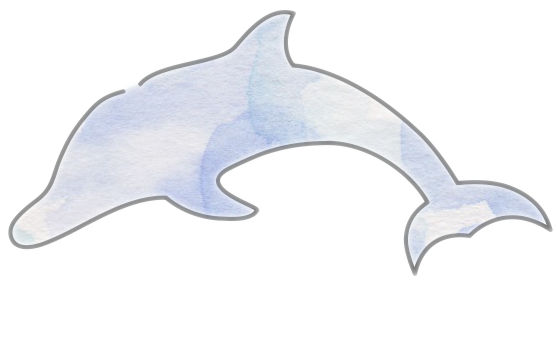

Ⅰ 聖者になんてなれない
器用だね、とに言われるたび、俺は少しずつ不器用になっていく。
彼女のとろりと濡れた、ぶどうの実のようなみずみずしい瞳には、何かの奥底を透かしとるような占いめいた機能はついていない。むしろそれは、見たものの表面をそのつどあるがまま裁断せずにはいられないような、融通のきかない正直な目だ。その目をもって、が俺を見つめ返す。絶妙に、頼りなく。わずかでも歪めばすぐ、塩っぽい水のしたたりが下睫毛の際にまで落ちてきそうで、そこに彼女が写しとった俺の輪郭を、けっしていたずらに裏切ってはいけないという張りつめた気持ちになる。
だけど、舌を這わせて歯を立てれば、はどこもかしこも甘いかじつの味がするのだ。
「イルミネーション、見たかった?」
ぱんぱんに詰まったスーパーの袋を後部座席からおろしながら、が振り向きざまに訊く。俺はその買い物袋をひとつ、ふたつと貰いうけながら、気のないふうに首を傾げてみせた。冬至を過ぎて、午後五時ともなれば辺りは十分に暗いが、俺たちは早々にドライブを切りあげてここに戻ってきている。重たい荷物をすべて俺に持たせてから、ケーキの入った包みと日中ずっと揺られていた茶色の紙袋を大切そうに腕に抱きかかえ、は余った手先でスライドドアを閉めた。
「見飽きました、十一月からどこ行ってもよう見るし」
「ほんとに。クリスマス前にお腹いっぱいになるよね」
の住むアパートは駅から遠く、エレベーターもついていない。五階まで自力でのぼってゆくしかないが、そのかわり部屋は広々としていて、ユニットバスもキッチンも新品の快適さがまだ残っている。
十二月二十四日、月曜、晴れ。近所の公園で待ち合わせていた俺に、は車道からクラクションをひとつ鳴らして手を振った。そのハンドルを握っているのはオトナの特権というやつだろうに、彼女はときおり、ずいぶんと子どもっぽいたわむれをする。親から譲りうけたという青いコンパクトカーはの相棒で、初めて二人で出かけたときも、彼女は俺をこの車に乗せ、神戸のベイエリアに連れていった。異性とどっかに出かけるといっても、近所のファーストフードだとかファミレス、あるいは電車で梅田に買い物にゆくぐらいしかしたことのなかった俺には、初手からして違う世界に導かれるような経験だった。のちに、「あれね、ちょっと気取っちゃったんだ。治くんの同い年の女の子に負けないように」と言われたが、その年上らしからぬ言葉のせいで、俺はますます彼女に引きずりこまれた世界から出てこられなくなってしまった気がする。
彼女の助手席で、俺は何もすることがない。ただと同じ景色を見て、同じ音楽を聴いて、たわいのない話をする。快晴の空を映した真冬の海を渡り、淡路島で魚を食べた。クリスマスイブに和食って変なの、と言いながら、はうまそうに刺身を口に運んだ。
二十四日の予定をから尋ねられたときは内心たまらなく浮かれたが、聖なる日の恋人たちの作法を自分がなにひとつ知らないことに、俺はたちまち気づかされた。例えば何を贈るべきなのか、とか。バイトもしたことのない高校生の予算なんてたかが知れている。年上の恋人に安っぽいものなど渡したくない。考えて、悩んで、けっきょく俺に贈れるものは小ぶりの花束ぐらいだった。朝十時の花屋で、何かいじらしいものでも見守っているかのような世話焼きの店員に助けられながら、予算いっぱいのクリスマスブーケをひとつ仕上げた。メッセージカードを添えてみたら、と子どもの使いのようにかいがいしく話しかけられ、つい首を横に振ってしまったのだけ心残りではあったけれど。
「それ、冷蔵庫に入れてもらっていいかな。ケーキも。ごめんね、適当で大丈夫だから」
アパートの部屋に着くやいなや、調達してきた食料品などそっちのけでは俺の渡した花束を丁寧に生けた。生けるといっても、そんな気取ったことは彼女にもできない。スーパーの二階の百円均一ショップでみつくろった花瓶たちや、コップに、彼女の感性で花々をわけていく。素人にしては上出来だと思った。日常のどんなささいなものも、の部屋にあるものはすべて、彼女の描いたルールに従って息をしている。統一感があって、美しい。俺の存在も、そうなんだろうか。彼女の調度品には連なりたくないなと、ふとそんな欲望がひらめいた。
「治くん、治くん。ちょっと来て」
キッチンカウンターの向こうから、が俺を呼んでいる。ベビーリーフとプチトマトのパックを冷蔵庫に入れてから、返事をせず振り返ると、が楽しげにリビングで俺をこまねいていた。ああ、とすぐに察しがついて、こそばゆい。少し大きめのショップ袋が、彼女の背には隠しきれていなかったから。
「はい。わたしも、治くんに」
両手で、腕をうんと伸ばして、仰々しく差しだされる。あげるほうも、もらうほうも、こういう瞬間はどこか照れくさいものだ。包みを飾るゴールドのリボンを、彼女はすぐほどくようにと俺をうながした。二人並んでソファに座り、急かされるがままに袋の中身を確かめる。彼女のくれたクリスマスプレゼントは、ざっくりと編まれたタートルネックのセーターだった。手のひらで撫でればウールの柔らかさが分かる、きっと俺の小遣いでは滅多に手の届かない、質の良いオフホワイトのニット。はにっこり笑って、俺の手からそれを取りあげると、俺の上半身にあてがうようにひろげてみせた。
「ねえ、いま着てみて。すっごく似合うと思う」
「……さんが、選んでくれたんですか」
「もちろん。いいでしょ」
どこか満足げに、自慢げに、がうなずく。間違いない、と自分の選択を確信しているふうに。それはこのセーターに対してか、このセーターに袖を通すことになる俺に対してなのか。着ていたカーディガンのボタンをはずしながら、ついさっきひらめいた欲望と寄り添って考える。花瓶にガーベラを飾るように、が俺にこのニットを着せたがるのだとしたら、それは少し憎たらしいことだ。憎たらしいぐらいに、平和なことだ。俺は衝動的に、脱いだカーディガンをソファのすみに押しやると、薄いシャツ一枚での上にのしかかった。
「おさむ、く」
口紅のとれてしまったのかたい唇に吸いつく。体温を注ぐように押しつける。不和を感じるのは最初だけで、あとはおのずとうまいぐあいにおもねってゆくから、心地いい。の手が、俺の肩を、首を、さすりながら引き寄せた。せっかくもらった上等なニットも、足もとのカーペットに投げだされ、はしたなく重なりあう人間のつがいをだんまり眺めてる。どうや、人間は愚かやろ。かなわんやろ。は、なんだか愛撫を受けながら笑っているようだった。唇を離すと、責めるようにではなく、からかうように上目遣いで睨まれる。彼女は俺の胸に、シャツに、ぬるい右手指を押しつけた。
「ねーえ、こら。着てくれないの」
「着ますよ。めっちゃ着ますけど、せっかく脱いだんで」
と言うと、はまたくすくすと笑って、その先の無礼をあっさりと俺に許した。許したというより、はなから許されていた。不意打ちも、行儀の悪さも、今はまだ抗うすべもなく、彼女をいろどる日常の一部。
つけたばかりのヒーターがゆっくりと部屋を暖めてゆくのを、外気に触れた肌で感じとりながら、俺たちはソファの上でややおざなりなセックスをした。は背中に鳥肌を立てていた。俺はそれを舌でなぞりあげて、うしろから彼女の奥にいれたり、出したりした。
それから、二人でつくった鍋をたらふく食べて、駅前で買ったショートケーキとチーズケーキを何かのしきたりのように半分ずつにしてつついた。テレビをつけて、話をして、そうこうしていると俺はやっぱり、たまらなくなってしまったので、もういちど、今度はもっとしたたかにを抱いた。ソファの上で目覚めたときには、俺は彼女が寝室から持ってきたのであろうブランケットにくるまっていた。不覚だ。リビングの掛け時計を見上げると、十時を回っていた。
「あー、起きちゃった」
はいつの間にかオーバーサイズの起毛パーカーとスウェットに着替えて、カーペットの上に体育座りになって俺を覗きこんでいた。赤い表紙のクロッキー帳を膝に抱えている。寝顔を描かれてしまったのだ、とぼんやり思って、自分の無防備さを恥じた。朝からずっと気張っていたとはいえ、これでは、平和ぼけしているのはどちらか知れない。
「そろそろ帰る支度したほうがいいね。明日も朝から部活?」
裸の胸がずくんと痛む。足を絡めあっているあいだは、歳の差など溶けてしまっているのに、こういうなにげない一言が現実をはっつけて襲ってくるのだ。五だか、六、だか。それ自体はべつにいい、なんでもない。がクラスメイトであればよかったなど、奇妙な妄想もしたためしはない。数えたくもない数字を振り払うように、俺は腕にちからを入れてソファから身を起こした。
「……正月って、さんこっちおりますか」
「うーん……年末年始は旅行で離れるから、帰ったらすぐ連絡するね」
「旅行って、どこです?」
「うん、ロンドン。お土産何がいいかなあ」
なんでもないふうにそう言われて、ちょお待てや、と思わずつっこみをいれてしまうところだった。どこかを思い描いていたわけでもないが、そんなあっさりと海外の都市名を口にされたら、予想などしていなくとも斜め上に引っ張りあげられてしまう。正月もひと目でいいから会いたい、手をつないで初詣に行きたい、そう、あわよくばと浸っていた夢はみごとにしぼんでいった。
「……え、誰と」
無様な疑問がぽろりとこぼれて、瞬間、しまった、と思えるほど頭も働いていない。はひらいたままのクロッキー帳を放ると、俺めがけてソファに飛び乗ってきた。ブランケットごとからだを抱きしめられる。それから、あやすように、の指が俺の前髪を撫でつけた。
「家族だよ。お母さんとお父さん」
いつか話の流れで聞いたことがある、の生まれ故郷のことだとか、育ちのこと、家族のこと。線ではなく、点として。彼女の暮らしぶりを見るに、それなりに裕福な家に生まれ育ったのだろうと想像はしていたが、どうも、年末年始を海外で過ごすようなご立派な家族が居るらしい。だからどうということもないのに、また胸の奥が膿むように痛んだ。一丁前に、距離を感じている。二人の距離。そういうものを、計らずにはいられないでいる。
「治くんの試合が見れないのが残念だけど。テレビでやるんだよね?」
まあ、と濁してうなずく。はスポーツに関しては全般からっきしだった。バレーのルールもよく分かってないし、春高なんて言ってもいまひとつぴんとこないだろう。むりに見てほしいとも、知ってほしいとも思わない。むしろ、知られたくないとさえ思っている。
なんとも言えない顔で押し黙った俺を、は照れているのだと勘違いしたらしい。彼女は幸せそうに笑う。美人なんよな、と思う。あんまり思いだすと平静を保てないと分かっているので、忘れるよう努めているが、ふとした瞬間にせりあがってくる。ここに棲む聞かん気のマモノの好物。不安というもの。
「がんばって。いっぱい応援してる」
ありふれた激励に、またひとつ俺はうなずいて、顔を上げた。
脱ぎ捨てたシャツと、カーディガンを羽織って、からもらったニットは丁寧にたたんでもとのショップ袋に仕舞いこむ。今度、いつになるか分からないが、と会うときに来ていこうと決めていた。のアパートから、家まで、徒歩二十分。車で送るというの申し出を断って、のぼせた頭を冷やしながら、ひとりの夜道を歩いたり走ったりして帰った。
心臓がベルのように鳴る。聖夜の鐘のように華やかでもなく、ひと足早い除夜の鐘のように厳かでもない。いうなればあの、なんでもない日に誰かのへまで鳴り響く廊下の非常ベルのように、鳴っている。そんな、ばかみたいに最高のクリスマスイブだった。
・
・
・
その異変に気づいたのは、元日の昼を過ぎたころだった。一月一日、火曜、曇り。朝早く叩き起こされ、正月の挨拶と、おせちやら雑煮やら腹いっぱい食わされ、ひととおりの儀式めいたものを済ませてから、ちょっとのつもりがベッドで数時間の居眠りをしていた。年が変わっても性根は変わらず、ものぐさな年初めだ。あくびをしながらからだを起こすと、部屋のクロゼットが開けっ放しになっている。侑か、と思った。あいつ、午後から初詣に行くとか言うとったな。彼女と二人で出かけるとかなんとか機嫌よく話していた。
侑のことを思いだし、なんとなく嫌な予感が胸にひろがったのと同じタイミングで、クロゼットの近くに、はさみと、白いタグが落ちているのを俺の寝ぼけまなこが捉えた。見つけてしまった。二段ベッドの下に居ることも忘れて、身を乗りだし、盛大に頭をぶつける。
――あいつ、やりよった。そういう男なのだ、双子の片割れのあのクズは。
「っきなり、何すんねん!」
夕方になって帰宅した侑を、俺は玄関で容赦なく突き倒した。突然のことに尻もちをついて、侑が非難の声を上げる。やつの焦げ茶色のピーコートの下には、オフホワイトのタートルネックがはっきりと覗いていた。俺の、からもらった、あの。死ね、と、それぐらいしか浮かばない。へらへらした顔で帰ってきやがって、馬乗りになって一発入れてやろうかと、寸でのところまで脳が沸騰していた。中学ぐらいまでよくあることだったが、きょうだい喧嘩など、いつまで経ってもほぼ殴り合いだ。
「……殺すマジで殺す」
「なっ……え、あ、これ着たん怒ってんの?」
「お前、っとに、金ッ輪際、俺の服を着るな、さわんな、クソボケカス死ね」
「なあんや、自分やってこないだ俺のモッズ無断で着とったやん。あれいくらした思ってんねんマジで」
少しも悪びれず、謝りもせず、鬼の形相で突き倒されてなおこんなことを言ってのける。侑のこういう態度を「憎めない」などと言う菩薩もいるが、少なくとも今の俺には憎しみしか湧いてこない。小刻みの震えが止まらない両手のこぶしで、一気呵成、俺は侑のコートにつかみかかった。そっくり同じ身長だが、今は玄関の段差があるぶんだけ、俺に分がある。
「っ……お前の、お前の見栄のカタマリみたいな服と一緒にすなや!!」
「はあ!?」
「とにかく死ね!!」
俺たちの怒号を聞きつけて、親父のそれ以上のカミナリが居間から落ちてきた。俺はもう一度、はっ倒す勢いで侑のコートを振り払い、二階に駆けあがった。恋人からもらった服に、自分より先に袖を通された。何かそれ以上の悔しさがつのっていた。いや確かに、それ以上のことだったのだ。は、俺に似合うと思って、あれを買ったのだ。お前じゃない。お前じゃない。お前のことなんか、は知らない。
たとえ、他人にはよくよく見わけもつかないほど、そっくりの外ヅラをしていたとしても。
「なあ……まだ怒っとるん」
数時間は経っただろうか、階下から夕飯の号令がかかっても反応もせず、部屋の電気もつけずにじっとベッドでふてていると、廊下の明かりがかすかに真っ暗な部屋に差しこんできた。久しぶりのまぶしさと一緒に、侑の声が降りかかる。ぺたぺたと歩み寄って来て、すぐ背後に気配が立ち止まった。どうするつもりかと思ったら、侑はまくらを遠慮げに引っ張って揺らしてきた。どっちもどっちのぐずり方。なんというか、俺もこいつも、ガキすぎて情けなくなってくる。
「なあー、なーあ、って。ごめんて。新品のタグ切ったのは悪い思ってんねんで? せやけど、どうしても着てみたかったんやもん。治、いつも貸してくれるし。あれ、かっこええし……」
しゅんとなるな。それでごまかそうとすな。余計に腹立つんじゃ、この調子こき。数時間寝かせても、心はろくでもないあくたいをいくらだって吐きだせる。らちがあかない。延々と駄々をこねているみたいに侑にまくらを揺らされ続けるのも不快で、俺はしぶしぶ頭をもたげた。きょうだい喧嘩なんて、いつも、どうやって折り合いをつけているのかほんとうに分からん。心はどうあれ、からだは同じ場所に帰ってくるしかないのが家族なのだから、正直者がばかをみるものなのかもしれない。相手に対してではなく、自分に対して。
「……いや。俺のほうこそ、いきなり突き倒してもうて、ごめんな」
やっとの思いでそう絞りだした。立つ腹と減る腹はまた別もので、こんなときも間抜けに空腹感を覚えている。ベッドから這いだすと、侑は俺の顔を覗きこむようにしながら横にくっついてきた。廊下と階段を照らす蛍光灯、久方ぶりの明るみが目に痛々しい。
「もう怒ってへん?」
「いや、怒っとるけど」
「怒ってんのかい」
「もうええわ。正月からぎゃあぎゃあ騒ぎたないしな」
そうだ、こいつとは。
数日後に迫っている大舞台のことがいやがおうにもよぎる。こんな子どもじみた乱闘をしている余裕があるのなら、はよ下ですき焼き食って、風呂入って、歯磨いて、さっさと寝るべきだ。イブも、正月も、喧嘩も、試合も、始まってしまえばあっという間に終わって、会えない時間もすぐに埋まる。
そう思わないとやってられない。そう思うからこそやっていける。
良いことも悪いことも、後悔も期待も、すべて忘れろ。からっぽの今だけを携え、いざ東へ。
top|next→
2017.12
Dolphin by Goker Cebeci
from the Noun Project / adapted.